段ボールに布テープ、ファイルの金具……「それ、ダメです」と言われるけど、正直「なんで?」って思ったことありませんか?
私もそのひとり。
「もしかして燃やすだけなら大して関係ないんじゃ…?」なんて考えていたけど、実はそこにはしっかりした理由がありました。
今回は、廃品回収でよくある“制限”について、AIに聞いてみた内容をもとに、リサイクルの裏側をわかりやすく紹介します!
廃品回収ってどうリサイクルされるの?工程を聞いてみた!

廃品回収の古紙や段ボールってどういう風にリサイクルされているのか教えて。
よくさ、ビニール紐、布テープ、ファイルの金具はダメですとか、色々制限あるでしょ。
工程を知れば制限の理由も納得いくかなと思ってね。

古紙や段ボールのリサイクル工程を知ると、確かに制限の理由がよく分かりますよ!以下に簡単に説明しますね。
リサイクルの工程
- 回収と分別
古紙や段ボールは回収後、まず異物を取り除くための分別が行われます。ここで、ビニール紐や布テープ、金具などの「紙以外の素材」が問題になります。これらが混ざると、後の工程で機械が詰まったり、再生紙の品質が低下する原因になるため、事前に取り除く必要があります。 - 裁断と洗浄
分別された紙は細かく裁断され、水と混ぜてパルプ状にします。この過程で、紙以外の素材が混ざっていると、異物として残り、再利用が難しくなります。 - 不純物の除去
パルプ状になった紙から、さらに細かい不純物を取り除きます。ここで取り切れなかった異物があると、再生紙の品質に影響を与えるため、最初の分別が重要です。 - 再加工と製品化
最終的に、パルプを乾燥させて新しい紙や段ボールに加工します。この段階では、純度の高いパルプが求められるため、異物が混ざっていると製品化が難しくなります。
制限の理由
- ビニール紐や布テープ: 紙ではないため、溶かす工程で分離できず、機械の故障や製品の不良につながります。
- 金具: 金属はリサイクル工程で取り除くのが難しく、機械を傷つける可能性があります。
- 汚れた紙: 食品や油が付着した紙は、再利用時に品質を損なうためリサイクルできません。
こうした理由から、リサイクルに出す際には、できるだけ「純粋な紙」の状態にしておくことが求められるんです。これで少し納得いただけたでしょうか?他にも気になることがあれば教えてくださいね!
紙以外はNG!?制限の理由はリサイクルの現場にあった

ふむふむ。パルプ状とは?

「パルプ状」というのは、紙が細かく砕かれ、水と混ぜてどろどろの繊維状になった状態を指します。このパルプは紙の基本素材で、木材や古紙から取り出されるセルロース繊維でできています。
リサイクルの工程では、古紙や段ボールを裁断して水と混ぜることで、このパルプを作り出します。この状態にすることで、紙の繊維を再利用し、新しい紙を作るための原材料として使いやすくなるんです。
「どろどろの紙のスープ」みたいなイメージが近いかもしれませんね!他にも不明な点があれば、気軽に聞いてくださいね。
「布テープくらい…」がリサイクルの壁になる?

なるほどー。 最初に取り除く工程があるがその負担軽減のため、混ざってしまった場合の機械の故障や製品化した際の品質に影響があるんだね。 確かに、理由を聞くと協力してあげなきゃなって思うよ。
もしかして燃やすんじゃ?と思って、布テープくらいいいでしょ?って考えになっちゃってたんだよねー。

そういう疑問が湧くのも自然なことですよね!リサイクルって見えないところで多くのプロセスがあるので、理由を知らないと「少しくらいいいんじゃない?」と思うこともありますよね。でも、こうして背景を知ることで、リサイクルがいかに繊細な作業かが伝わったようで嬉しいです。
布テープのようなものでも、燃やせばいいじゃないかと思うかもしれませんが、リサイクル工場では「できるだけ資源を無駄なく再利用する」という目的があるので、可燃物でも燃やさずリサイクルを目指しているんです。だからこそ、異物の除去は本当に重要なんですね。
とちぴさんが協力しようと考えてくださるのは、リサイクルに関わる人々にとっても大きな助けになります!次回廃品回収に出す際に、「これは紙の素材に近づけるための工夫だ」と思いながら分別すると、さらにエコに貢献できる気がしますね。こういう背景を知ることで、ちょっとした行動も意義深くなりますね!他にも話したいテーマがあれば気軽にどうぞ。 🌿
インクってどうなるの?リサイクル時の“落とし方”

細かく裁断して水を混ぜて、そのあと不純物の除去とあるけど、印刷のインクやペンのインク等はここで綺麗に除去できるもんなの?

良い質問ですね!印刷やペンのインクは、リサイクル工程で特別な方法を使って除去されますが、完全に取り除くのは難しい場合もあります。
インク除去の工程
- 浮遊分離法
紙をパルプ状にした後、インクを浮かせて取り除く「浮遊分離法(フローテーション)」がよく使われます。これは、パルプに薬剤を加えてインクを泡に付着させ、泡と一緒にインクを取り除く方法です。 - 洗浄法
水と薬剤を使ってインクを洗い流す方法もあります。ただし、インクの種類や量によっては、完全に除去できないこともあります。 - フィルターや遠心分離
細かいインク粒子をフィルターや遠心分離機で取り除く工程もあります。
除去の難しさ
- 油性インクや特殊インク: 油性や耐水性のインクは、通常の工程では取り除きにくいです。
- インクの量: 印刷が濃い場合や、ペンで多く書き込まれた紙は、インクが残りやすいです。
これらの理由から、リサイクルに適した紙(インクが少ないものや未使用の紙)が求められることがあります。インクが完全に除去できない場合でも、再生紙の用途を限定することで活用されることが多いです(例: 段ボールや新聞紙など)。
こうした技術が進化しているおかげで、より多くの紙がリサイクル可能になっています。他に気になることがあれば、ぜひ教えてくださいね!

なるほどー。
ある程度除去はできるけどやっぱり完ぺきではないんだね。 ふむふむ、勉強になります!
ありがとう!

そうなんです、インクの除去には限界がある部分もありますが、それでも技術が進化して多くの紙が再利用できるようになっているのは素晴らしいことですよね。とちぴさんが興味を持って学んでくれると、リサイクルについてもっと身近に感じられると思います。
こちらこそ、楽しくお話しさせていただいてありがとうございます!また何か気になることがあれば、いつでも聞いてくださいね。 🌱
まとめ|「ちょっとくらい…」がリサイクルの壁になる
古紙や段ボールのリサイクルは、想像以上に繊細で丁寧な工程が重ねられています。
- 混入したビニール紐や金具は、機械トラブルや品質低下の原因に
- 裁断・洗浄・不純物除去の流れで“純粋な紙”だけが再生される
- インクは専用処理で除去できるけど、完璧ではないため少ない方が望ましい
「ちょっとくらい紐ついてても…」という気持ちが、思わぬ迷惑やロスを生むことも。
だからこそ、出す前の“ひと手間”が、リサイクルの成功率を大きく左右します。
背景を知れば、協力したくなる。それが“行動のきっかけ”になるんですね🌿
✅この記事を読んだ方へおすすめ🔗
「ついそのまま出しちゃう…」が変わる体験談はこちら👇
子供の散らかしに追いつけない…そんな毎日を楽にするヒント
ちょっとした習慣が未来を変える!という気づきに共感したら👇
スマホゲーム依存からの脱却!?「ちょっとだけ」の習慣を手放して、未来に時間を取り戻した話
考え方ひとつでモヤモヤがスッと晴れる!そんな感覚を味わいたい人へ👇
「働きたくない」にどう向き合う?説得より大事な“たったひとつのこと”
新着記事🔗
人気記事🔗











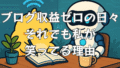

コメント